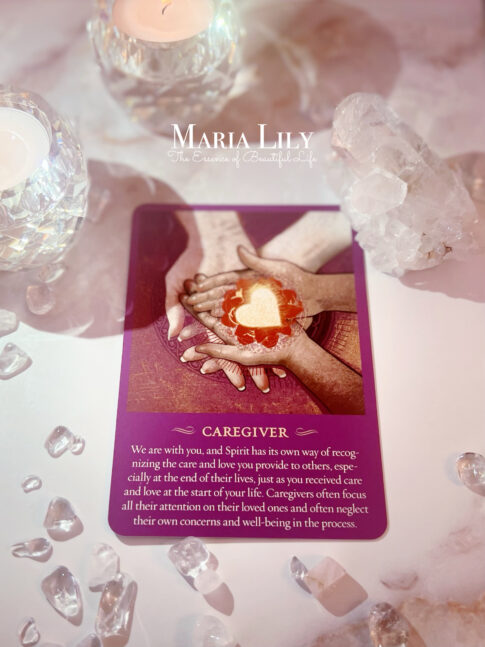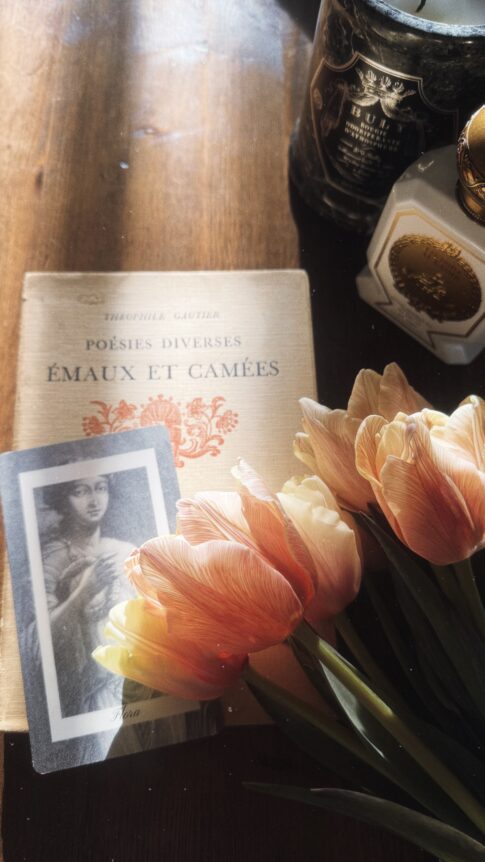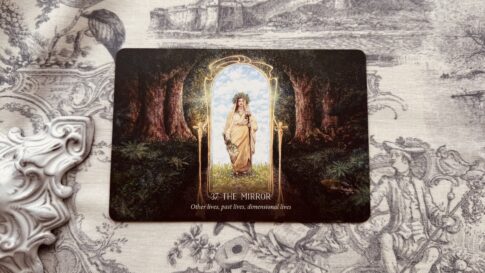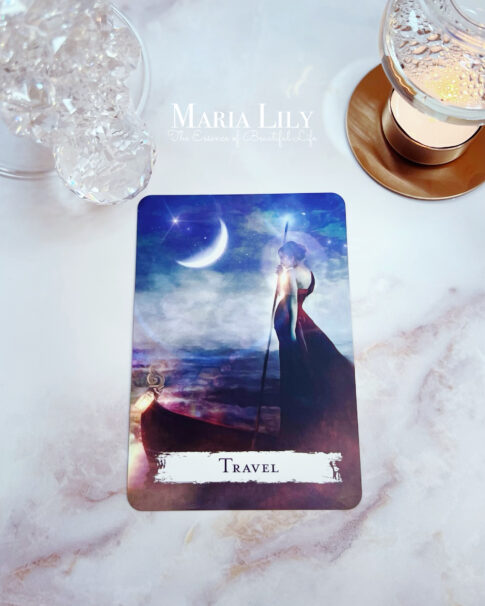Part.1はこちらからお読みください👇
四人目:エリザベス1世
女帝と皇帝の二面性を持つ統治者
エリザベス1世(イングランド女王)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
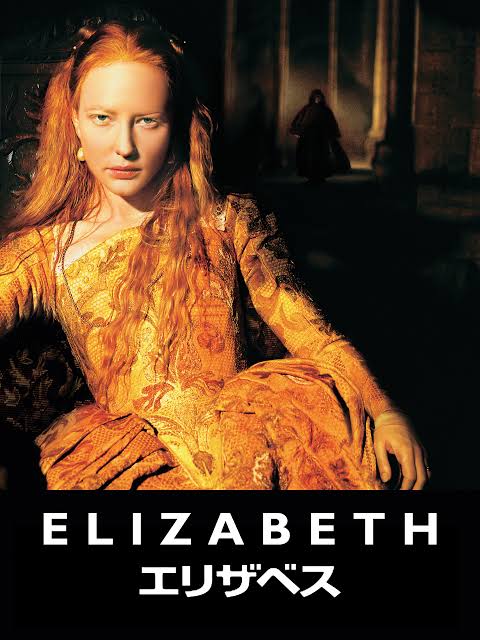
🎞️映画 『エリザベス』
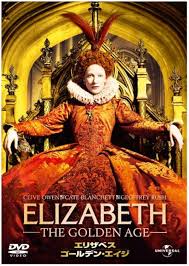
🎞️映画『エリザベス ゴールデン・エイジ』

🎞️映画『2人の女王 メアリーとエリザベス』
16世紀後半のイングランドを導いたエリザベス1世の物語は、今を生きる私たちの心に深く響きます。
ヘンリー8世とアン・ブーリンの娘として生まれた彼女は、幼い頃から波乱に満ちた運命を生きることになりました。
男性が当然のように王位を継ぐ時代に、一人の女性として国を導くということ。それは、並々ならぬ覚悟と強さを必要とする道でした。
生涯独身を貫き、”処女王”として歴史に名を残したエリザベス1世。
彼女は一人の女性として、確かに結婚や愛を求める気持ちを持っていました。しかし、最終的に国の安定を選び、個人の幸せを手放す決断をします。
タロットで例えるなら、「女帝」の持つ豊かな感性と直感力を活かしながら、「皇帝」のような毅然とした統治力も併せ持つという、稀有な存在です。

『エリザベス ゴールデン・エイジ』より
エリザベス1世が独身を貫いた理由
彼女の生涯独身という選択の裏には、複雑な要因が絡み合っていました。
まず、16世紀のイングランドでは、女性が単独で王位に就くこと自体が異例でした。
自身の母アン・ブーリンが王妃でありながら処刑された悲劇を目の当たりにして育ったエリザベスには、「結婚すれば、夫が実質的な権力を握り、自分の立場が危うくなるかもしれない」という切実な危機感がありました。
夫を迎えることは、国内外の勢力バランスを大きく揺るがすことを意味します。場合によっては王配(夫)が実質的な支配者となり、エリザベス自身の権限が制限される可能性さえありました。独身であり続けることは、国政の主導権を確実に自らの手に保つための、賢明な選択だったのです。
さらに、当時の王家の結婚は、純粋な愛情だけでなく、国家間の同盟関係にも直結する重大事でした。
エリザベス1世は、プロテスタントの国教会を守りながら、ヨーロッパのカトリック諸国との関係も維持するという、極めて繊細な立場にありました。
カトリックの王子との結婚は、国内のプロテスタントの反発を招きかねません。一方、プロテスタントの王子との結婚は、スペインやフランスといったカトリック大国との関係を決定的に悪化させる恐れがありました。
エリザベスは、複数の縁談を外交的な駆け引きの道具として巧みに利用しながら、最終的な結婚は避けることで、この微妙なバランスを保ち続けたのです。

『エリザベス ゴールデン・エイジ』より
エリザベス1世と同時代を生きた二人の女王
メアリー1世(イングランド女王)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
エリザベス1世の統治の本質を理解する上で、同じ時代を生きた二人の女王との比較は、深い示唆を与えてくれます。特に、同じ父ヘンリー8世を持つ異母姉メアリー1世との対比は興味深いものです。
メアリー1世は、ヘンリー8世と最初の妃キャサリン・オブ・アラゴンの間に生まれ、生涯を通じて強いカトリック信仰を持ち続けました。
後に“ブラッディ・メアリー(血のメアリー)”という異名を取ることになる彼女の治世は、信仰と権力が交錯する激動の時代でした。
1553年から1558年までのわずか5年間の統治期間で、メアリー1世は強固なカトリック復古政策を推し進め、多くのプロテスタントを処刑・弾圧してしまいました。その苛烈さから、人々から畏怖の念を持って見られるように。
彼女は自身の宗教的信念と、カトリックの血筋としての正統性を絶対的なものと考え、周囲の声に耳を傾けることをしませんでした。
これはまさに「自分が信じることが唯一の正義」というエゴが暴走し、溺れるように、王としての柔軟性を失った例と言えます。
短い治世の中でこれほどの流血を招いたのは、権力を手にした時に、私情と信仰のみを振りかざし、国家全体の調和という大きな視点を見失ってしまったからではないでしょうか。
メアリー・スチュアート(スコットランド女王)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
もう一人の重要な存在が、スコットランド女王メアリー・スチュアートです。エリザベス1世とほぼ同時代を生きた彼女は、複雑な政治・宗教の対立の中で波乱の人生を送りました。
16世紀半ば、スコットランドではプロテスタントの宗教改革が急速に進み、多くの貴族がカトリック王家に反発する状況が生まれていました。
そんな中、カトリックとしてフランスで育ったメアリー・スチュアートがスコットランド女王に即位し、国内のプロテスタント勢力との対立が激化します。

『2人の女王 メアリーとエリザベス』より / スコットランド女王メアリー・スチュアートとその夫
さらに、メアリーはヘンリー7世(エリザベス1世の祖父)の血筋を引くことでイングランド王位の継承権を主張できる立場でもあり、カトリックを奉じる彼女が「正当なイングランド女王」を自称する可能性をエリザベス1世が警戒したため、両女王の緊張はますます高まっていきました。
特にエリザベス1世は母アン・ブーリンとの結婚が正当かどうかを疑われやすい立場にあり、カトリック勢力からは庶子扱いされていた面もありました。
そうした背景から、スコットランド女王メアリー・スチュアートはエリザベス1世にとって大きな脅威として映ったのです。

『2人の女王 メアリーとエリザベス』より / イングランド女王エリザベス1世
国内外の情勢が複雑に絡む中、メアリー・スチュアートは最終的に反乱や失脚を経てイングランドへ亡命するものの、そこでエリザベス1世によって幽閉され、遂には処刑されるという悲劇的な末路を辿りました。
メアリー・スチュアートは、愛や情熱といった個人のエゴに振り回され、周囲の支持を得られなかったという意味で、 溺れたまま浮上できなかった王と言えるかもしれません。

『2人の女王 メアリーとエリザベス』より / スコットランド女王メアリー・スチュアートとその夫
映画『2人の女王 メアリーとエリザベス』で描かれる二人の関係は、「女王」としての在り方の対照性を鮮やかに映し出しています。
メアリー・スチュアートは3度結婚し、息子を一人出産しますが、政治に愛と信仰を、そしてしばしば私的な感情を絡めるあまり、政権基盤が揺らぎました。
映画のクライマックスとも言える、エリザベスとの初対面のシーンでは、天然痘の痕を白いメイクで隠したエリザベスが、若く美しいメアリーへの嫉妬を一瞬見せながらも、メアリーの内なるエゴを見抜いた瞬間に「女」から「統治者」へと鋭く転換する姿がとても印象的でした。

『2人の女王 メアリーとエリザベス』より / イングランド女王エリザベス1世
ちなみに、メアリー・スチュアートの息子であるジェームズ6世(スコットランド王)は、やがてイングランド女王エリザベス1世が後継者なく1603年に崩御したのを受けて、「ジェームズ1世」としてイングランド王位を継承するに至ります。
こうしてスコットランド王ジェームズ6世と、イングランド女王エリザベス1世の血筋がひとつに結ばれ、両国は同じ国王を戴く「同君連合」の状態となりました。なんとも複雑な関係性ですね・・・
真のリーダーシップとは?
この二人のメアリーは、それぞれ異なる形で「溺れる王」の姿を体現しました。
メアリー1世は権力やカトリック信仰に、メアリー・スチュアートは愛と情熱に溺れ、結果として国家や周囲とのバランスを失っていきました。

『エリザベス ゴールデン・エイジ』より
対照的に、エリザベス1世には、女性としての欲望や愛、信仰を、王としての政治課題とあえて切り離す冷静さがありました。
最初にも述べたように、エリザベス1世は、「女帝」に象徴される優美さや直感力を活かしつつ、「皇帝」として統治力を行使する決断力と高度なバランス感覚を持っていたのです。
なぜなら、エリザベス1世の統治は決して理想化された美しい物語だけではないからです。
王位への脅威を徹底的に排除するため、時として血縁者をも犠牲にする厳しい選択を迫られ、いとこを幽閉し死に至らしめるなど、今日の視点からすれば残酷とも言える政治的措置を取ることも実際にあったのです。
これは感情に任せた無差別な弾圧ではなく、より計算された政治的な判断であり、まさに冷徹な「皇帝」の在り方そのものです。

『エリザベス ゴールデン・エイジ』より
エリザベス1世のこうした容赦のない選択の積み重ねが、44年もの長期政権を可能にし、イングランドの繁栄を支える土台となったことは確かです。
こうした歴史的真実は、リーダーシップの本質について私たちに深い示唆を与えてくれます。
真のリーダーシップとは、時として理想と現実の狭間で、困難な決断を迫られることがある。しかし、より大きく長期的な目標のために、前に進む勇気を持つこと。
それこそが、エリザベス1世が私たちに残した最も重要な教訓なのかもしれません。
現代を生きる女性たちへ
三人の女王の物語、とりわけエリザベス1世の生き方は、時代を超えて私たちの心に響きます。
時代は大きく変わりましたが、今を生きる女性たちもまた、様々な役割の間でバランスを取ることを求められています。
「仕事で結果を出しながら、母として子育ても完璧にこなさなければ」「キャリアを積みつつ、家庭も大切にしたい」「リーダーとしての強さを見せながら、女性としての優しさも失いたくない」――。
このような期待やプレッシャー、様々な価値観の狭間で揺れ動く中で、私たちは時として「溺れそう」になります。
特に現代では、SNSを通じて溢れる「理想の姿」との比較に苦しみ、周囲の期待に応えようとするあまり、本来の自分を見失いそうになることも少なくありません。
しかし、エリザベス1世が教えてくれるのは、自分の中の「女帝」と「皇帝」、両方の力を認識し、受け入れることの大切さです。時と場合に応じて、柔軟に、しかし芯はぶらさずに生きていく――。

The Medieval Europe Tarot
たとえ「溺れそう」になったとしても、内なる「女帝」の直感力と「皇帝」の意志力、この二つの力のバランスを保ち続けることで、必ず浮上への道は開かれていくはずです。
大切なのは、完璧を目指すことではなく、自分らしい形でバランスを取り、誰かの評価や期待に縛られることなく、自分の人生の真のリーダーとして歩んでいくこと。
私たちは皆、自分自身の人生という「王国」の統治者なのです。その統治の形は、一人一人が自分らしく決めていけばよいのです。

The Medieval Europe Tarot
最後に、「溺れる王」の亜種をご紹介し、終わりとしましょう。
五人目:太陽王ルイ14世の光と影
ルイ14世(フランス王)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
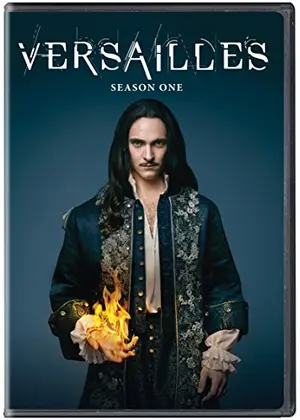
🎞️ドラマ『ヴェルサイユ』
17世紀フランスが生んだ最も華麗な君主、ルイ14世。自らを「太陽王」と名乗り、ヴェルサイユ宮殿に比類なき宮廷文化を築き上げた絶対君主です。
ドラマ『ヴェルサイユ』は、その輝かしい表面の下に潜む、陰謀と孤独、そして一人の人間としての苦悩を鮮やかに描き出しています。

ドラマ『ヴェルサイユ』より
このドラマの特筆すべき点は、ルイ14世という異色の「溺れる王」の姿です。通常、王のエゴが暴走すれば、それは必然的に破滅へと向かうもの。しかし彼の場合、まるで水面すれすれを泳ぎ続けるかのように、沈むことなく王であり続けます。
強烈な自己主張で周囲を支配しながらも、常に陰謀に怯え、疑心暗鬼に苛まれる。それでいて決して絶対王政という理想を曲げることはありません。
「朕は国家である」という発言から、まさに「王=国」という強烈なエゴの同一化を感じさせます。彼の存在、彼のエゴ、彼の権力は、もはや王個人の存在を超え、フランスの国家そのものと結びついていたのです。
彼の姿は、まさにタロットの「太陽」と「月」の両面性を体現しているかのようです。

Wisdom of Pooh Tarot
「太陽」のごとく眩いカリスマ性を放ちながら、その影には「月」が象徴する不安と恐れが常に付きまとっています。
王座を奪われる恐怖、周囲の裏切りへの懐疑、それらの影に怯えながらも、なお光り輝き続けようとする姿には、独特の緊張感が漂います。
もし彼がエゴを完全に手放していれば、より穏やかな統治も可能だったかもしれません。しかし、ルイ14世にとって「太陽王」とは、単なる称号以上の、存在そのものでした。
「沈まない王」であるために、彼は燃え続けることを選んだのです。その結果、フランスは確かに強国となりましたが、その代償として国内は戦争と贅沢な宮廷生活で疲弊していきます。

「私は王である」この強固な自意識を決して手放さないルイ14世の姿は、従来の「溺れる王」の物語とは一線を画しています。
エゴの放棄による救済という定石を覆し、むしろエゴを燃料として燃え続けることで、独自の道を切り開いていくのです。
光と影を抱えながら頂点を目指し続ける彼の姿からは、王としての孤独と、一人の人間としての生々しい苦悩が伝わってきます。

ドラマ『ヴェルサイユ』より
『ヴェルサイユ』は本当に面白くて夢中になって見ました。おすすめのドラマです。煌びやかなヴェルサイユ宮殿、衣装、ヘアスタイル、全てが夢中にさせてくれました。ドロドロの人間ドラマも見逃せません。
ということで、五人の「溺れる王 / 王女」を紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたら幸いです。そして、興味を持たれましたら、是非、映画やドラマを楽しんでみてくださいね☺️
最後までお読みいただき、ありがとうございます。